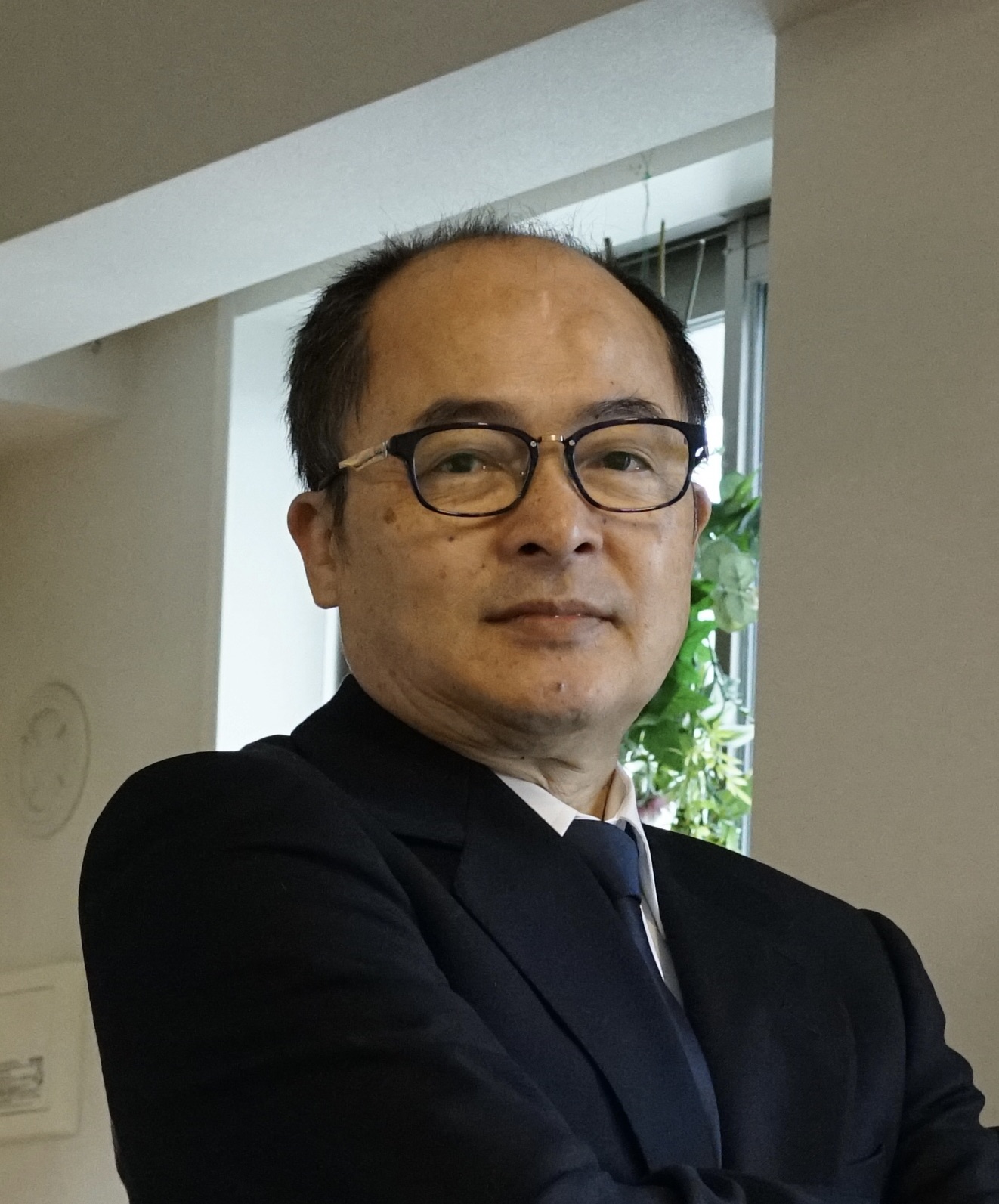過去に起こった問題は、特に製造業では過去トラと呼ばれています。過去トラとは過去のトラブルのことで、一般的には過去のトラブルを参考にすることで、同じような問題を再発させないようにしたいと考えています。
しかし、このように過去トラを使い切れている企業はそれほど多くないことが分かっています。過去トラはどのように扱われていますか?と質問すると、サーバーにトラブルの報告書が保管してあります。或いは、トラブルが発生した際には、速やかに社長以下の幹部社員や課長まで一斉メールで伝達していますとの返事が返ってきます。
では、過去トラの内容として、どのようなことが書かれていますか?そして、対策や結果まで記録されていますか?とお聞きすると、実は、その点については十分フォローできていないとのお答えがよく聞かれます。
このようなことがないように、どのように過去トラブルを扱い、活用すると良いのかについて、具体的に解説をしていきます。
今回、過去トラの生産技術での利用について考えてみることにしました。
生産技術の役割とは
生産技術とは何を役割とする部門なのかといえば、設計の考えている製品を具現化する技術であり、その技術により品質コストを最良にした工程と設備の設計をすることです。品質とコストを最良にするためには、社内のこれまでの知識経験と外部から学んだことなどから常に新たな生産技術開発に努めなければなりません。
人は失敗から得られたことから進歩するもので、生産技術は工程や設備設計の失敗、その設計で生産する製造現場の日常の問題点、製品設計のミスに気づかないで、信頼性を確保できなかった図面検討漏れの3つの分野で発生した問題を解決することで成長するものだと考えています。
設計と製造にまたがるポジションにある機能は大変重要だと思います。
生産技術の明確な組織がない企業では、設計にその機能が含まれている、或いは製造側にその機能が含まれていると思います。
このいずれにせよ、主たる機能は設計すること、或いは生産することになり、生産技術面に主体があるように企業規模が小さい場合にはできないこともあります。
生産技術を独立化しない場合には、生産技術の主たる業務は設備調達になっているはずです。
間接部門の価値は利益をアップすること
製造業の間接部門の仕事の評価が未だあいまいですが、企業の利益向上に責任があると考えるべきでしょう。一方、製造側は売上に責任があるということになるでしょう。
間接部門に設計も調達も生産管理も生産技術も含めて考えると、そこには業務の流れが繋がっているはずです。
しかし、きっちりとした繋がりではなく、人に依存した業務プロセスがたくさん組み込まれており、本来ITなどで情報を共有ハンドリングすべきことも人による処理が多いと思います。
では、この属人化した業務プロセスをつなぐには何をすれば良いかですが、それは先に述べました設計、生産技術、製造の問題点を共有解決することだと思います。解決することの中で、業務プロセスや判断方法の間違いに気づくことができるからです。
これらの問題点は人が行う業務であるから発生したものと考えることが自然です。つまり問題点は結果を表しているからです。
このように問題点(過去トラ)の未然防止に取組むためには、業務プロセスとその判断を正しくする必要があります。
まとめ
過去トラはこのように生産技術が中心となって設計と製造の業務プロセスを繋ぎ、品質とコストを最良にする大変重要なきっかけだと思う必要があります。
業務に問題のないことはありません。だから問題が起こり、その解決を繰り返すことで組織集団における個人の考えが揃っていくことができるからです。
誰でも完全な設計や生産はできるはずはなく、隠れた問題の発生因子を発見し、大問題となる前に対策をすることが必要です。
以上のように、業務プロセスの繋がりを正しくし、利益を最大化するために貢献することが生産技術での過去トラの利用にあると思います。